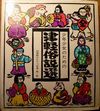嶽の大人
岩木町の幡副というところに、小山重という鍛冶屋がありました。
ある日、仕事も終わって、寝ていますと、真夜中に、どんどんとくぐり戸をたたくものがあります。
弟子が出てみますと、「赤倉から鉄棒の注文にあがりました。八日までにでがしてくれ。」というので、
親方に聞くと、「引き受けろ。」というので、そのとおり使いの者につたえて、帰しました。
親方は、次の日から、注文の鉄の棒を作りはじめました。長さが二メートル、重さが二四〇キロもある鉄棒ですから、弟子と七日がかりで、ようやく作りあげました。
約束の八日の日、弟子三人にいいつけて、赤倉沢のお堂まで運ばせました。三人はお堂の前にすわって、まっていましたが、なかなか受け取りにきません。
あたりが暗くなったころ、やっと一人の大男があらわれて、
「よくとどけてくれた。ごちそうしよう。」と、火をおこし、クシに魚をさして、焼いて食わせました。
三人はおそくなったので、そこのお堂に泊ってしまいました。朝になってみると、いつの間にか鉄棒はなくなって、三人のそばには、たくさんの銭がおいてあります。
お堂のなげしを見ると、三尺もある大わらじがぶらさがっており、あたりのしげみは、大男にふみつけられて、山奥まで道ができていました。
三人はびっくりして、山道をはしるように村に帰りました。
「鉄棒は、たしかに大男にわだしました。」と、三人は親方にいいましたが、昨夜見たことは、とうとう親方に、うちあけませんでした。話すと、あとでいったい、どんなことが起こるか、心配でたまらなかったからです。
あとで、そのことをきいた村の人たちは、「それは、赤倉の大人が注文した鉄の棒だろう。」とうわさしあったということです。
上の話は、津軽地方に伝わる岩木山の大人の話の一つです。大人というのは、山に住む巨人のことで、このほかにも、大人の話はたくさんのこっています。
さて、「津軽俗説選」の著者は、嶽の大人と題して、次のように書いています。
岩木山の嶽温泉に大人というものがすんでいて、さまざまな怪異をなす。と言われています。
大人に出会ったという人の話をきくと、大人というのは、どうやら人間でないように思われます。
八甲田の酢香湯では、死人があると、きゅうに風雨が起き、なにものかが死骸を取っていってしまう、ということですが、これも大人のしわざだろうと、いわれています。
そうなると、大人というのは人間ではなく、『本草綱目』にある魍魎と、同じものに思われます。
魍魎というのは、山や川にすむ化け物のことです。
鬼沢村(弘前市)には、大人が使った鍬が残っているといわれていますが、これは、人並みはづれて力の強い、むかしの百姓が使った鍬だと思います。
また、兼平山の下に、大人の足あとがのこっているといわれていますが、これも田圃に大きな足形をした窪地ができたのを、大人の足あとと、いいつたえただけだと思います。
岩木川の杭戸の淵の上に、鬼の足あとがついた石がありますが、これも足形が自然についたものにすぎません。
出典: 少年少女のための津軽俗説選
編集: 弘前市立弘前図書館
発行: 弘前図書館後援会
鬼神太夫と大人の談
むかしから、町や村には、めずらしい伝説や、かわったいわれがあります。これも、その一つです。
◎「鬼神大夫」(十腰内のいわれ)
むかし鰺ヶ沢(西津軽郡)のちかくに、とても力の強い、鬼神太夫という刀をつくる、鍛冶屋がすんでいました。
刀を打ったあとが、現在も湯船(いまの西津軽郡鳴沢の湯船部落)、床舞(いまの西津軽郡森田村床舞)にのこっています。
鬼神太夫は、心をこめて、十本の刀をつくりました。「これは、われながら会心の作だ。」と、じまんしていました。
が、あるとき、その中の一本が、まるで翼が生えたよう鳥のように、近くにある杉の大木に飛び移ったのです。
すると、不思議なことに、杉の木はそれ以後、夜でも妖しく、光りかがやくようになったではありませんか。人々は、仰天しました。
「この刀は、神さまだ。」
「杉の木に、神さまが、乗り移ったんだ。」
と、うわさしながら、杉の木をうやまうようになったといいます。
しかし、鬼神太夫が打った刀は、一本欠けたので、九本しかありません。
「せっかく十本、まとめてつくったのに。」
鬼神太夫は、とても残念でした。刀は、腰にさすものです。それが、一本たりないので十腰(十本)は無いわけです。
それで、十腰ないーーーこの刀を打ったのが、いまの弘前市十腰内だといわれます。(湯船も床舞も十腰内も、鰺ヶ沢に近い部落で、となりあっています。)
さて、鬼沢の神社の、御神体は、鬼神大夫がつくった太刀だといわれます。
◎「大人の談」
むかし、弘前の鬼沢に、一人の木こりがすんでいました。
ある日、木こりは山道で、大男(大人)と出あいました。はじめは、とてもこわかったのですが、大男は、にこにこしています。
木こりは、大男と、したしくなりました。
毎日、木こりは山に出かけると、大男と相撲をとってあそびました。
木を切るのも忘れて、大男とばかり遊んで、夕がたに、手ぶらで家にもどりました。
が、どうしたことか、うら庭に、二~三日分もはたらいて運んでくるほどの、薪が、つまれてあるではありませんか。
「どうしたことだ?」
木こりは、おどろきました。これはきっと、大男が木こりのために、そっと山から木を切って、もってきてくれたのにちがいありません。木こりは、大男の、やさしい気持ちに感謝しました。
でも、山に行くと、やっぱり大男と、相撲をとってばかりいます。毎日毎日、相撲ばかりとって遊んでいるうちに、とうとう木こりも、大男になって、そのまま姿をけしたといいます。
『寰宇記』という本に、洛山に、木客というものがすんでいたと記してあります。
木客とは、鬼のなかまで、人間のかたちをして体が大きく、人のことばもよく話すということです。
木客は、いつも木の実ばかり食べていたので、とても長生きをしました。ときどき、村里にもおりて来て、無断で、人家に入って酒をのみました。
木客は、きっと鬼の大男にちがいありません。木こりが、相撲をとった大男も、鬼だったのでしょう。
出典: 少年少女のための津軽俗説選
編集: 弘前市立弘前図書館
発行: 弘前図書館後援会